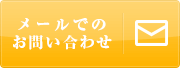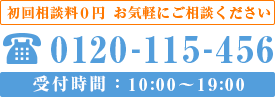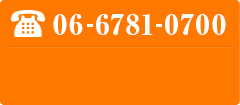NO.38 相続登記未済不動産と破産
<事案>
14年前に亡くなった父名義の自宅土地建物(遺産分割協議済、相続登記未済)が存在したが、破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 2社
残債務額 約2,000万円(住宅ローン残債務を含む)
財産 特になし
<最終的な結果>
Aさんの財産を調査したところ、Aさんの母と居住している自宅が亡くなった父の登記名義でした。亡父の相続人は、Aさん、母、姉の3人ですので、法定相続なら、自宅は母2/4、Aさんと姉が各1/4ずつの共有(注1)となります(民法900条1項)。Aさんが、自宅の共有持分を有しているなら、財産ありとなり同時廃止事件(注2)として申立をすることはできません。
Aさんに確認したところ、「父が亡くなった後、私、母、姉の3人で自宅を母の所有にする遺産分割協議が成立しました。でも、費用がかかることがわかったので、登記はしませんでした。だから父の名義のままになっています」とのことでした。遺産分割協議が成立しているならば、父死亡時から自宅は母名義になっており(民法909条)、Aさんの財産ではありません。
以上の次第を丁寧に報告書にまとめ、遺産分割協議書などの資料を裁判所に提出することで、特に問題なく破産手続きは問題なく進み、無事免責決定がされました。
<担当者から>
財産はないとAさんから聞いていたので、自宅の登記を見た時は驚きました。依頼者様からの聞き取りと資料などからの調査・確認は、並行して進めていかないといけないな、と改めて思いました。
【用語説明】
(注1)「共有」 「共有持分」 (民法249条以下)
共有とは、複数の所有者(=共有者)によって支配・利用されている状態。
持分とは、各共有者が目的物に対する有する割合のこと。
(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく、破産手続の費用の捻出ができない場合に、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。裁判所の書面審査のため、原則申立時に必要資料をすべて提出し、事細かに報告する必要がある。
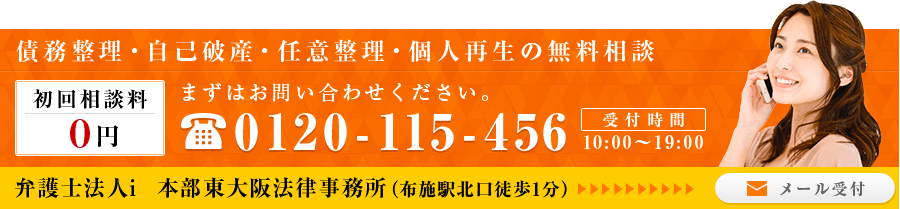
- NO.678 浪費と自己破産
- NO.677 自営業の不振と自己破産
- NO.676 経費の自己負担と自己破産
- NO.675 生活費と自己破産
- NO.674 生活保護と破産
- NO.672 浪費と破産
- NO.670 病気による生活保護と破産
- NO.669 生活保護と破産
- NO.666 病気と自己破産
- NO.664 生活費と自己破産
- NO.661 住宅ローン・高級車購入による破産
- NO.659 債務整理 ⇒ 【破産】・生活保護と破産
- NO.650 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.646 債務整理 ⇒ 【破産】・ギャンブルと破産
- NO.645 債務整理 ⇒ 【破産】・後見人と破産
- NO.643 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.642 債務整理 ⇒ 元妻のうつ病により返済が困難となった事案と破産申立
- NO.641 債務整理⇒破産手続開始申立事件
- NO.639 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立
- NO.637 債務整理 ⇒ 少額のギャンブルと家族の一人が財産管理する特別事情と免責
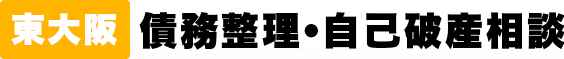
![弁護士法人i[アイ]](https://h-osaka-saimu.com/wp-content/uploads/common/LogoI.png)