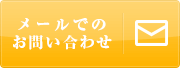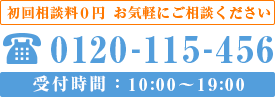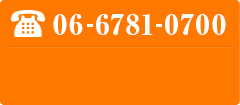NO.36 破産申立の影響(確定拠出年金)
<事案>
自宅と退職金受取があったため破産管財事件(注1)として申立をしたが、破産開始決定後に確定拠出年金(注2)の存在が判明し、自由財産(注3)とされた事案。
<解決に至るまで>
債権者数 12社
残債務額 約2,000万円(住宅ローンを含む)
判明した財産 確定拠出年金 判明時残高約700万円
<最終的な結果>
Aさんには自宅と退職金があり、財産があるので、個人の破産管財事件(注1)として破産申立をする必要があります。個人の破産管財事件の場合、自由財産(注3)と自由財産拡張(注4)により認められた財産を除き、破産開始決定時に存在する破産者の財産は破産財団(破産法34条1項)となり、破産管財人に管理処分権があります(破産法78条1項)。
Aさんは、20年以上勤務してきたので、確定拠出年金の残高もかなりの金額になっています。金額が多額であることと、Aさんの将来の年金に関わることですので、入念に調査し、破産管財人と裁判所に、差押禁止財産であるので自由財産となり破産財団に属さないとの報告書と資料を提出しました。
その結果、破産管財人から、Aさんの確定拠出年金は自由財産であるとの回答があり、破産管財人に処分されることはなくなりました。
その後破産手続きは問題なく進み、無事免責決定がされました。
<担当者から>
「破産したから財産全部なくなる」と一度は聞いたことがあると思います。これは正しくありません。確かに、破産者が破産開始の時に有する一切の財産は破産財団となります(破産法34条1項)。しかし、破産財団に属さない財産もあります(同条3項)。このあたりは専門的な知識が必要になりますので、ご自身で判断される前に、弁護士に何なりとお尋ねください。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務があります。
依頼者さんと直接会わずに債務整理事件を受任することは、原則できないのです。
弁護士に債務整理の相談をしたいとお考えであれば、お近くの足を運びやすい法律事務所に相談されることをおすすめします。
【用語説明】
(注1)破産管財事件(破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
法人代表者の場合、必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合、破産管財人への引継予納金として20万5,000円の納付が必要となる。
(注2)確定拠出年金(確定拠出年金1条)
私的年金の一種。勤続中に掛金を確定して拠出し、拠出金の運用を指示して、老後に運用の結果に基づいた給付を受ける年金。
(注3)自由財産(破産法34条3項2号)
破産財団に帰属しない財産のこと。差押禁止財産などがあたる。破産者が管理・処分できる。
(注4)自由財産拡張
個人破産の場合に、破産者の経済的再生のため、破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは、預金、保険、退職金、自動車、敷金。拡張が認められると、破産管財人に処分されず、破産者の財産として保護される。
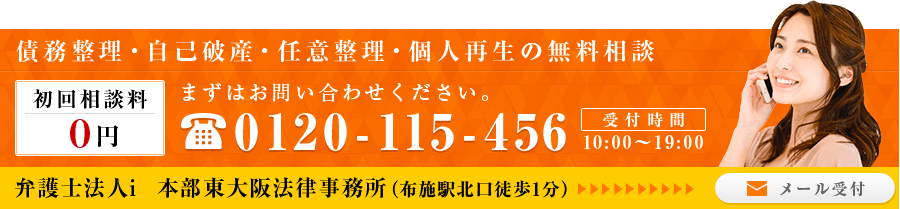
- NO.679 会社経営者の破産
- NO.678 浪費と自己破産
- NO.677 自営業の不振と自己破産
- NO.676 経費の自己負担と自己破産
- NO.675 生活費と自己破産
- NO.674 生活保護と破産
- NO.672 浪費と破産
- NO.670 病気による生活保護と破産
- NO.669 生活保護と破産
- NO.666 病気と自己破産
- NO.664 生活費と自己破産
- NO.661 住宅ローン・高級車購入による破産
- NO.659 債務整理 ⇒ 【破産】・生活保護と破産
- NO.650 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.646 債務整理 ⇒ 【破産】・ギャンブルと破産
- NO.645 債務整理 ⇒ 【破産】・後見人と破産
- NO.643 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.642 債務整理 ⇒ 元妻のうつ病により返済が困難となった事案と破産申立
- NO.641 債務整理⇒破産手続開始申立事件
- NO.639 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立
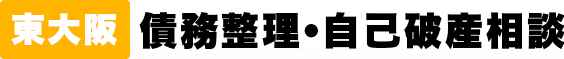
![弁護士法人i[アイ]](https://h-osaka-saimu.com/wp-content/uploads/common/LogoI.png)