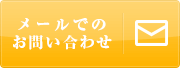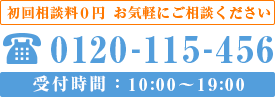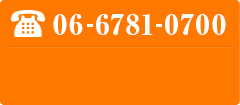NO.37 亡夫の相続債務と破産
<事案>
自身の債務と2年前に亡くなった夫から相続した債務につき、破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 8社
残債務額 約1,700万円(亡夫からの相続債務を含む)
財産 特になし
<最終的な結果>
Aさんの夫は、2年前に約1,000万円の債務を残して亡くなり、Aさんご自身の債務も700万円ほどありました。亡くなってから2年経過しているので、夫の債務については、相続放棄(注1)ができません。また、最後の支払から5年以上が経過している債務が多く消滅時効(注2)も検討しましたが、訴訟提起と一部支払による時効中断自由(注3)があったため、時効援用もできませんでした。そのため、多くの債務が残り支払不能の状態で、やむなく破産申立をしました。
債務額は大きく、相続債務については資料がないものもあり、丁寧に調査して申立書を作成し、わかりにくい点については報告書で補足説明をするなどして申立を行いました。
その結果、特に問題なく破産手続きは問題なく進み、無事免責決定がされました。
<担当者から>
なかなか難しいですが、配偶者が亡くなり、債務がある可能性があれば、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。相談の時期が早ければ、処理方法の幅が広がります。
【用語説明】
(注1)「相続放棄」 (民法939条)
相続人が、家庭裁判所に申述をすることで、被相続人の権利や義務を一切受け継がないとする手続き。申述は、相続開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要がある。
(注2)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
貸金業者の債務は、最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後、援用することで効果が発生し、債務の支払を免れる。なお、消滅時効援用は、後日の証明のため、内容証明郵便でされることがほとんどである。
(注3)「時効中断事由」
時効期間の進行を中断する事由。具体的には、請求、差押、承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合、請求(訴訟提起)、承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。
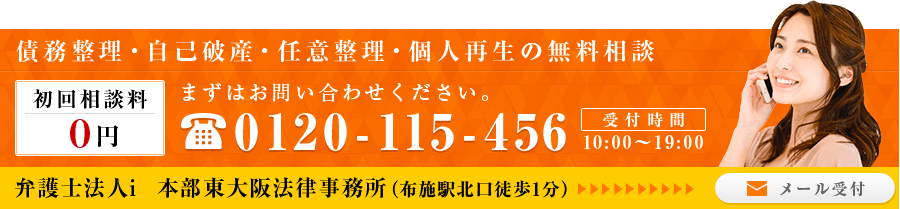
- NO.679 会社経営者の破産
- NO.678 浪費と自己破産
- NO.677 自営業の不振と自己破産
- NO.676 経費の自己負担と自己破産
- NO.675 生活費と自己破産
- NO.674 生活保護と破産
- NO.672 浪費と破産
- NO.670 病気による生活保護と破産
- NO.669 生活保護と破産
- NO.666 病気と自己破産
- NO.664 生活費と自己破産
- NO.661 住宅ローン・高級車購入による破産
- NO.659 債務整理 ⇒ 【破産】・生活保護と破産
- NO.650 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.646 債務整理 ⇒ 【破産】・ギャンブルと破産
- NO.645 債務整理 ⇒ 【破産】・後見人と破産
- NO.643 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費と破産
- NO.642 債務整理 ⇒ 元妻のうつ病により返済が困難となった事案と破産申立
- NO.641 債務整理⇒破産手続開始申立事件
- NO.639 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立
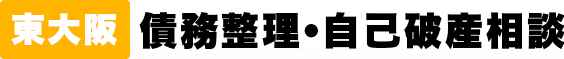
![弁護士法人i[アイ]](https://h-osaka-saimu.com/wp-content/uploads/common/LogoI.png)